玉ねぎは家庭菜園でも人気の高い野菜ですが、長い栽培期間の中で特に重要なのが「追肥の時期と方法」です。
「家庭菜園 玉ねぎ 追肥 時期」と検索しているあなたも、きっと「いつ追肥すればいいのか」「何回与えるのか」「どの肥料が良いのか」など、具体的な管理方法に悩んでいるのではないでしょうか。
追肥のタイミングを誤ると、トウ立ちや肥大不良、さらには貯蔵性の低下といった問題につながることもあります。
この記事では、玉ねぎの追加肥料の時期はいつですか?という疑問をはじめ、玉ねぎの追肥は何回必要ですか?玉ねぎの止め肥はいつ頃しますか?など、初心者がつまずきやすいポイントをわかりやすく解説します。
また、米ぬかや鶏糞、化成肥料の使い方や、追肥を忘れた場合の対処法まで、家庭菜園に役立つ具体的な情報を網羅。
玉ねぎの肥料不足によるサインや、追肥 遅いとどうなるかといった注意点にも触れながら、あなたの栽培成功をサポートします。
「玉ねぎ 石灰 追肥は必要?」「玉ねぎ追肥 おすすめはどれ?」といった細かい疑問にも対応した内容となっていますので、ぜひ最後まで読んで、あなたの玉ねぎ栽培に活かしてください。
この記事の内容
- 玉ねぎの品種別に適した追肥の時期
- 追肥の回数と止め肥の重要性
- 使用する肥料の種類と使い方
- 追肥を忘れた場合や遅れた場合の対処法
家庭菜園の玉ねぎの追肥時期の基本
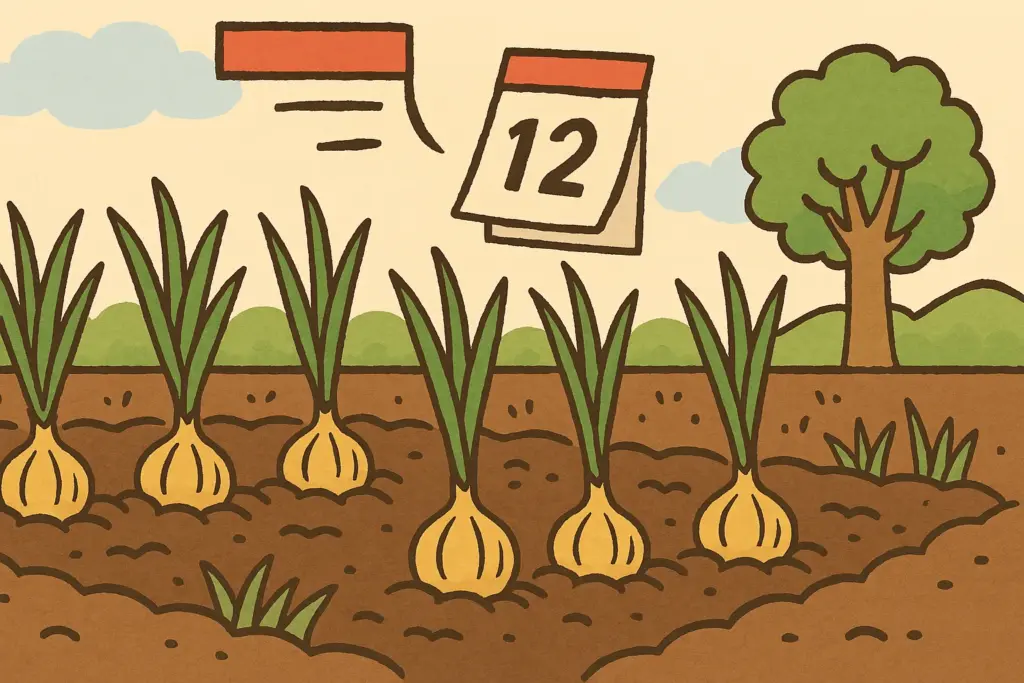
※画像はイメージ:家庭菜園の時間
玉ねぎの追加肥料の時期はいつですか?
玉ねぎの追加肥料は定植後2週間おきを目安に行うのが基本です。
玉ねぎは植え付けから収穫までの期間が長く、ゆっくりと成長していく野菜であるため、長期にわたり安定した栄養補給が必要です。
特に冬の間は地上部の成長が鈍化しますが、春になって気温が上昇すると一気に球が大きくなります。
そのときに必要な栄養分をあらかじめ蓄えておくためにも、定期的な追肥が重要となります。
例えば、早生品種であれば12月中旬と2月上旬の2回、中生および晩生品種であれば1月上旬、2月中旬、そして3月上旬の3回の追肥が目安になります。
ただし、地域やその年の気候によって生育状況は異なるため、葉の色や勢いなどを観察しながら適切なタイミングを見極めるようにしましょう。
実際には、目に見えて葉色が薄くなってきたときや、成長が止まっているように感じたときが追肥のサインともいえます。
玉ねぎの追肥は何回必要ですか?
玉ねぎの追肥回数は育てている品種によって異なります。
一般的には、極早生から早生品種では2回、中生や晩生品種では3回の追肥が適しています。
理由としては、栽培期間の長さと球の肥大が始まる時期に差があるからです。
例えば、極早生種は栽培期間が比較的短いため、初期に必要な栄養を補ってしまえばその後の追肥は最小限で済みます。
一方で、中生や晩生種は春になってから本格的に球の肥大が始まるため、より長期間にわたって栄養を供給する必要があります。
そのため、3回に分けて計画的に追肥を行うことで、品質の良い玉ねぎに育てることが可能になります。
また、回数以上に大切なのは、各追肥のタイミングです。
与える時期が遅れると効果が薄くなったり、逆にトウ立ちの原因になったりする可能性もあるため、育てている玉ねぎの様子をこまめに確認しながら施肥のスケジュールを調整するようにしましょう。
玉ねぎの止め肥はいつ頃しますか?
止め肥の時期は、一般的には3月上旬が最も適切とされています。
なぜなら、この時期は玉ねぎが春の訪れとともに急速に球を肥大させ始める直前にあたるからです。
このタイミングでしっかりと最後の追肥をしておくことで、以降の成長期に必要な栄養を十分に蓄えることができ、球の形成がスムーズに進みます。
逆に、止め肥が遅れてしまうと、玉の成熟が不完全になりやすく、結果として収穫した玉ねぎの品質が下がる恐れがあります。
例えば、3月中旬や下旬に追肥をしてしまった場合、玉が過剰に育ってしまったり、葉が茂りすぎて病害虫が発生しやすくなることもあります。
さらに、遅い時期の追肥によって、肥料の効きが収穫期までに切れず、貯蔵性が著しく低下する可能性も否定できません。
これらの理由からも、止め肥は3月上旬までに必ず済ませておくことが、良質な玉ねぎを収穫するためには不可欠です。
追肥が遅いとどうなる?
何度目の正直よ。今度こそ玉ねぎがちゃんと育ちますように❤︎
過去3年間の原因
↓↓↓
原因1:追肥の時期が遅すぎた
原因2:浅く植えすぎた
原因3:雪が多くて追肥が出来なかった今年は甘70を300本、赤玉ねぎを60本植えました(60本買ったはずが3本足りなかったぞ)
#家庭菜園初心者 #玉ねぎ栽培 pic.twitter.com/gIM9b4q356
— ゆー@家庭菜園初心者 (@yukateisaien) November 9, 2024
追肥が遅れてしまうと、さまざまな悪影響が玉ねぎに及びます。
特に問題となるのは、春の成長が加速するタイミングで必要な栄養が不足しやすくなることです。
このため、球の肥大がうまく進まず、小ぶりな玉になってしまうケースが多く見られます。
また、必要な時期を過ぎてから追肥を行うと、栄養過多によって逆に成長が乱れ、トウ立ちと呼ばれる現象が起きやすくなります。
これは、玉ねぎが花芽をつけてしまう状態で、可食部の品質が大きく損なわれます。
例えば、3月下旬や4月に入ってから追肥をすると、球が締まりに欠け、保存中に腐敗しやすくなることもあります。
さらには、葉ばかりが茂ってしまい、肝心の球が肥大しない「徒長」状態になることも少なくありません。
これらのリスクを避けるためには、計画的な施肥スケジュールを立て、早めの対応を心がけることが大切です。
理想的には、気温が安定し始める3月初旬にはすべての追肥を完了させておくのが望ましいです。
玉ねぎの肥料不足のサインとは
玉ねぎの肥料不足は、見た目に明確なサインとして現れます。
特に、葉先が黄色く枯れ込んできたり、葉全体が薄くなってツヤがなくなったりする場合は、チッソやカリウムといった主要な栄養素が不足している可能性があります。
このような症状は玉ねぎが健全に生育できていない証拠であり、早急に対処することが大切です。
例えば、葉の伸びが明らかに悪くなった、根元が細く頼りなくなっていると感じた場合も、肥料不足が原因であることが多いです。
特に家庭菜園では、天候や土壌の状況によって肥料の吸収効率が変動するため、こまめな観察が欠かせません。
私であれば、葉色や成長具合を確認し、肥料不足の兆候を感じた時点で速やかに対策を講じます。
具体的には、速効性のある液体肥料を使用して様子を見るほか、化成肥料を少量ずつ複数回に分けて施す方法をとります。
これにより、植物へのストレスを抑えながら必要な栄養を補うことができます。
ただし、注意点として、必要以上に肥料を与えると過剰障害を引き起こすおそれがあるため、施肥量は必ず適正範囲内に抑え、過不足のない管理が求められます。
バランスの取れた施肥を心がけることで、玉ねぎは順調に育ち、収穫時には大きくてしっかりとした球を実らせることができるでしょう。
家庭菜園の玉ねぎの追肥時期のやり方

※画像はイメージ:家庭菜園の時間
ポイント
玉ねぎ追肥のおすすめ肥料は?
玉ねぎに向いている肥料はバランスの良い化成肥料やアミノ酸入りの肥料です。
理由は、玉ねぎの生育にはチッソ・リン酸・カリウムがバランスよく必要で、これらを均等に含む肥料が効果的だからです。
これらの成分はそれぞれ役割が異なり、チッソは葉の成長を促し、リン酸は根の発達と球の肥大をサポートし、カリウムは全体の抵抗力と品質を高めます。
例えば、8:8:8の化成肥料はこの3要素をバランスよく含んでおり、初心者にも扱いやすい製品です。
市販されているものには、さらにアミノ酸やミネラルが配合された専用肥料もあり、これらは玉ねぎの味や保存性を高める効果も期待できます。
また、ゆっくり効くタイプの緩効性肥料を使えば、施肥の手間を省くこともできます。
どちらを選ぶかは栽培スタイルや予算、使用するタイミングにより異なります。
例えば、こまめに手入れできる方であれば通常の化成肥料でも十分に対応できますが、手間をかけたくない方や忙しい方には専用の緩効性肥料が適しているかもしれません。
家庭菜園初心者には、使い方が明確で失敗が少ない専用肥料の使用をおすすめします。
鶏糞を使った追肥の方法
ここでは、鶏糞を使った追肥について詳しく説明します。
鶏糞は有機質が非常に豊富で、玉ねぎの甘みや風味を向上させる効果があるとされています。
特に、土壌に長く残ってゆっくりと効くため、持続的な栄養供給が期待できるのが特徴です。
ただし、使用する際は必ず完熟タイプの鶏糞を選ぶようにしましょう。
未熟な鶏糞はアンモニアの影響で根を傷めることがあるほか、匂いが強くて近隣の迷惑になることもあります。
例えば、1㎡あたりひと握り程度を目安に、株元にまいてから軽く土と混ぜるようにして施用します。
鶏糞は肥料成分が濃いため、多く施しすぎると肥料焼けを起こすこともあるので、量には十分注意が必要です。
また、臭いが気になる場合や、住宅が密集している地域で使用する場合には、追肥のタイミングを夕方や風の少ない日に行うなど、周囲への配慮も大切です。
鶏糞は環境にも優しい天然素材の肥料なので、適切に使用すれば玉ねぎの質と収穫量の両方を高めることができる心強い資材といえるでしょう。
米ぬかを使った追肥は効果ある?
例えば、米ぬかには豊富な有機質が含まれており、土壌改良に非常に有効な素材です。
特に、微生物の活動を活発にする効果があるため、土の中の環境が整い、玉ねぎの根が張りやすくなるという利点があります。
加えて、米ぬかにはミネラルやビタミン、脂質などの栄養素も含まれており、それらが土壌中の微生物の栄養源として作用することで、土壌全体のバランスが良くなります。
このようにして健康な土壌が育つと、結果的に作物の病気予防や収量の安定にもつながります。
ただし、米ぬかの効果は比較的緩やかに現れるため、即効性を求める追肥としてはやや不向きです。
発酵が進むことで一時的に窒素が土壌から奪われる「窒素飢餓」現象が起きることもあるため、使用するタイミングや量には注意が必要です。
私であれば、米ぬかは主に元肥として使用し、栽培前にしっかりと土に混ぜ込んでおく使い方を選びます。
また、補助的な追肥として使用する場合には、量を控えめにし、他の肥料と併用することでバランスを取るようにしています。
主な追肥としては、やはり化成肥料など即効性のあるものを使うのが安心です。
化成肥料の使い方とポイント
化成肥料の基本的な使い方としては、1㎡あたり約40gを目安に施用するのが一般的です。
施肥の際には、畝間や株元にまいてから軽く覆土することで、肥料が雨や水やりで流れ出すのを防ぎつつ、根の近くまでしっかりと届かせることができます。
特にマルチ栽培の場合は、植え穴に一つまみずつ肥料を入れる方法が効果的で、土壌への直接接触が少なく済むため、肥料焼けのリスクも低減できます。
また、施肥するタイミングとしては、風の強い日を避け、水やり後など土がやや湿っている状態で行うと、肥料の飛散を防ぎ、根への吸収率も高くなります。
こうすれば、根に直接栄養が届きやすく、玉ねぎの生育をしっかりと支えることが可能です。
ただし、化成肥料は効果が早く出る一方で、過剰に与えると根を傷めたり、肥料成分が土壌中に蓄積しやすくなったりするため、必ずラベルに記載された使用量を守ることが大切です。
定期的な観察と、必要に応じた調整を行うことで、より安定した収穫が期待できるでしょう。
玉ねぎに石灰の追肥のタイミング
玉ねぎに石灰を施すのは、追肥というよりも主に元肥や土壌改良の目的で行われる作業です。
なぜなら、玉ねぎは酸性土壌に非常に弱く、適正なpH値である5.5〜6.5の中性に近い環境で最もよく育つからです。
酸性の強い土壌では、根の働きが鈍くなり、必要な栄養素の吸収が妨げられるため、初期生育に大きな影響が出てしまいます。
そこで、植え付けの1〜2週間前を目安に苦土石灰を1㎡あたり100〜150gほどまき、しっかりと耕しておくことが推奨されています。
こうすることで、土壌全体のpHバランスが整い、カルシウムやマグネシウムなどの微量要素も補給されるため、健康な根の発育が促進されます。
追肥の段階では石灰を使用することはほとんどありませんが、例外的に土壌pHが急激に低下した場合や、連作障害などが懸念される状況では、少量の石灰を追加で施して微調整を行うこともあります。
特に雨が多く降った後などは、酸性に傾きやすいため注意が必要です。
石灰は一度に多量に与えると根を傷める原因になることもあるため、使用する際はpH計で土壌の状態を確認してから行うようにしましょう。
あくまで石灰は“予防的な調整材”という位置づけで使うと効果的です。
追肥を忘れた場合の対処法
もし追肥を忘れてしまったとしても、慌てる必要はありません。
適切なタイミングでリカバリーすれば、大きな収穫への影響を最小限に抑えることができます。
まず確認すべきは、玉ねぎの生育状況です。
例えば、葉の色が淡くなっていたり、根元が細くて頼りないと感じた場合は、明らかに栄養不足のサインといえます。
このようなときは、速効性のある液体肥料を使うことで、短期間で栄養補給が可能になります。
また、固形の化成肥料を使う場合でも、焦って一度に大量を施すのではなく、少量ずつ数回に分けて施肥するのが安全です。
段階的に施すことで、急激な栄養変化による根のダメージを防ぎ、安定した吸収を促すことができます。
さらに、追肥を行う時間帯としては、日差しの強い昼間を避けて、早朝や夕方など涼しい時間帯に施すと、根への刺激が少なく安心です。
ただし、追肥のタイミングがあまりに遅れると、玉ねぎの肥大が間に合わず、最終的な球のサイズや貯蔵性に影響が出ることがあります。
特に3月以降の遅い時期に慌てて追肥を行うと、トウ立ちのリスクが高まるため注意が必要です。
したがって、追肥を忘れたと気づいたら、なるべく早めに対応することが大切です。
天然植物活力液【HB-101】の活用方法
野菜・果実・米・茶・花・樹木と、すべての植物栽培にお使いいただける天然植物活力液「HB-101」。
農園はもちろん、家庭菜園・ガーデニング・ベランダ園芸など、植物を育てるすべての方におすすめです。
【HB-101】は、スギ、ヒノキ、マツ、オオバコのエキスを抽出・精製し、混合した天然植物活力液です。
HB-101は、植物の活力化、土壌の改善、そして植物の免疫力を高めるという3つの効果を持っています。
植物の活力化については、葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み、細胞を活性化させます。
これにより、植物は青々とした葉、丈夫な茎と根を育てることができます。
また、HB-101は土壌のバランスを整える効果もあります。
有効微生物の繁殖を助け、土壌中のバランスを保つことで、健康な土壌づくりに役立ちます。
特に、マルチングを行った後の安定した土壌環境では、HB-101の効果がさらに持続しやすくなります。
さらに、植物の免疫力を高め、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果によって、病気や害虫から植物を守ることができます。
千葉県や山梨県の農業試験場でも、その効果が実証されており、特に成長初期やストレスがかかった際に使用すると、より効果を発揮します。
※クリックすると公式サイトに飛びます
畑のレンタルサービスもおすすめ
家庭菜園を始めたいけれど、庭やスペースがない場合には、畑のレンタルサービスを利用するのも一つの方法です。
レンタル畑では、季節ごとの野菜の種や苗、重たい肥料もあらかじめ用意されています。
お客様の声を反映した作付計画に基づき、病害虫に強く収穫量の多い高品質な品種を厳選して提供してくれます。
また、畑には重たい農具や持ち運びにくい刃物もすべて常備されています。
クワやスコップ、剪定バサミ、防虫ネットなど、必要な道具や資材が揃っており、初心者でも栽培を成功させやすい環境が整っています。
さらに、農具の使い方や栽培方法についても丁寧に教えてもらえるため、学びながら家庭菜園を楽しむことができます。
特に、シェア畑![]() のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。
のようなサービスでは、化学農薬を使わず、有機質肥料を使用して自然の力でおいしい野菜を育てることが可能です。
収穫した野菜はその場で安心して食べることができ、新鮮な旬野菜を食卓に並べることができます。
※クリックすると公式サイトに飛びます
家庭菜園で玉ねぎの追肥時期に押さえるべきポイント

※画像はイメージ:家庭菜園の時間
ポイント
- 追肥は定植後2週間おきが基本
- 冬の成長は緩やかで春に一気に肥大する
- 早生品種は12月と2月の2回が目安
- 中生・晩生品種は1月・2月・3月の3回が目安
- 育てる品種によって追肥回数は異なる
- 止め肥は3月上旬までに済ませるのが望ましい
- 遅れた追肥はトウ立ちや球の品質低下を招く
- 肥料不足は葉色の変化や成長鈍化で判断できる
- 液体肥料や少量の化成肥料で速やかに対応可能
- おすすめはバランス型の化成肥料(8:8:8など)
- 鶏糞は完熟を使用し量を控えめに施すと効果的
- 米ぬかは土壌改良向きで追肥には不向き
- 化成肥料は土と混ぜて株元へ施すのが基本
- 石灰は元肥で使い、追肥では基本的に不要
- 追肥を忘れても早期に対応すれば大きな問題にはならない






